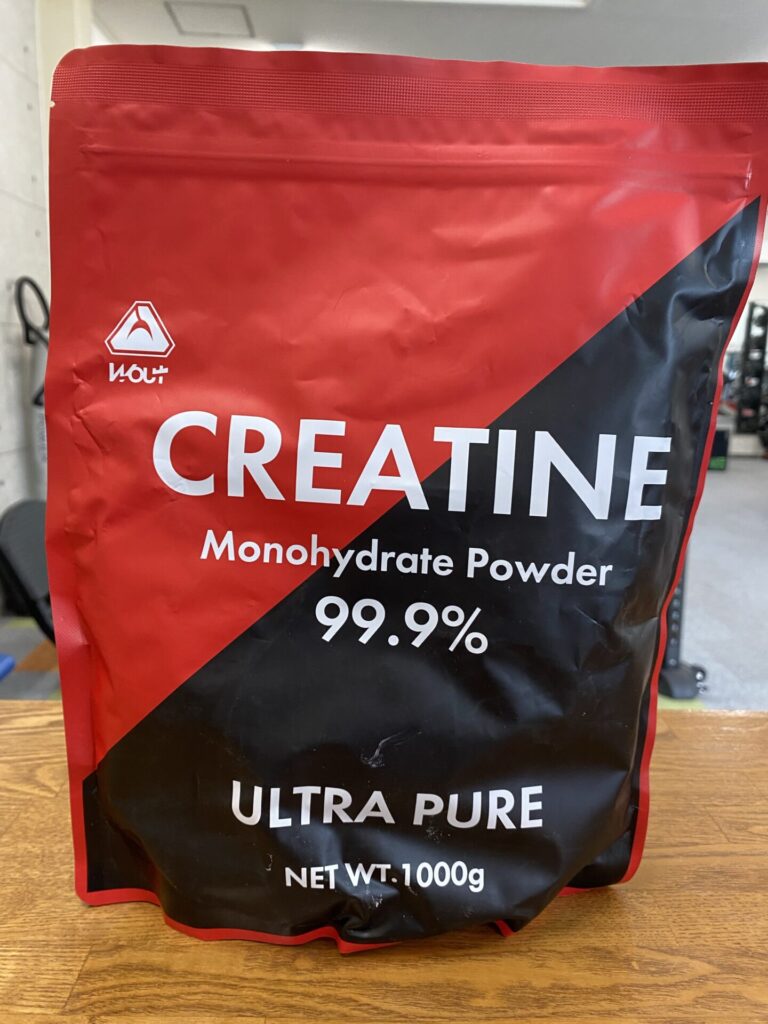
2025年7月1日から、クレアチンの摂取を再開しました。
これまで減量中ということもあり、体重増加を懸念してクレアチンは控えていました。しかし、最近のトレーニングで「出力が上がらない」「レップ後半で粘れない」といった感覚が続き、明らかにパフォーマンスに影響が出ていました。
そんなタイミングで、Amazonのタイムセールにて1kgのクレアチンが大幅に安くなっていたため、迷わず購入。必要性を感じていたこともあり、すぐに摂取を再開することにしました。今回は「クレアチンローディング」からスタートし、1日20g(5gを4回に分けて)を5日間摂取。その後は、5g/日で維持摂取を継続していく予定です。
クレアチンとは?筋トレ愛好家とアスリートの定番サプリ
クレアチンは、体内でアルギニン・グリシン・メチオニンというアミノ酸から合成される物質で、主に骨格筋に存在しています。筋肉内では「リン酸クレアチン」として保存されており、ATP(アデノシン三リン酸)の再合成を助ける役割を担います。
ATPは、筋収縮などのエネルギー源となる物質ですが、すぐに枯渇してしまいます。ここでクレアチンが補助的なエネルギー供給源となることで、高強度・短時間の運動パフォーマンスが持続しやすくなるのです。
牛肉や魚などの動物性食品にも含まれていますが、トレーニング効果を最大限に引き出すためには、サプリメントによる補給が効率的とされています。
科学的エビデンスが示すクレアチンの効果
クレアチンは、スポーツサプリメントの中でも最も研究が進んでいる成分のひとつです。以下のような効果が、多くの論文で確認されています。
高強度運動のパフォーマンス向上
クレアチン摂取により、ベンチプレスやスプリントなどの短時間高出力運動における出力が約8〜14%向上するという報告があります(Kreider et al., 2017)。
筋肥大と筋力増加の促進
筋力トレーニングと併用することで、除脂肪体重や筋断面積が有意に増加することが確認されています(Branch, 2003)。
神経保護作用や認知機能サポートの可能性
高齢者や神経疾患を対象にした研究では、脳機能や認知機能に対するポジティブな効果も示唆されています(Avgerinos et al., 2018)。
このように、クレアチンは筋力トレーニングにおける補助サプリメントとしてだけでなく、健康維持や脳神経系にも幅広い効果が期待されています。
減量中にクレアチンを抜くべきか?
「クレアチンを摂ると体重が増えるから、減量中は避けたほうが良い」と思っている方は少なくないかもしれません。
確かに、クレアチンは筋細胞内の水分保持を促進するため、摂取開始から数日で1〜2kg程度の体重増加が起こることがあります。しかしこれは水分が筋肉内に引き込まれることによる健全な増量であり、脂肪が増えるわけではありません。
逆に、減量中こそクレアチンを摂取することで以下のようなメリットがあります。
筋力の維持
筋分解の抑制
トレーニング強度の維持
集中力やパフォーマンスの安定化
つまり、「体重の数字」だけを気にして摂取を控えるのは、本末転倒とも言えるのです。
クレアチンの摂取方法:ローディング vs 毎日摂取
今回は「再開」であったため、筋肉内の貯蔵量を早く満たす目的で、いわゆる**クレアチンローディング(1日20g×5日)**を選びました。
ただし、初めて摂取する方や胃腸の弱い方には、毎日5gずつの継続摂取の方が無理がなく、おすすめです。両者の違いは以下の通りです:
ローディング摂取:1日20gを5日間続けることで、約1週間で筋肉内のクレアチン濃度が飽和し、効果を早く実感しやすい。ただし、胃腸への負担を感じる人もいる。 毎日摂取:1日5gの摂取を3〜4週間続けることで、自然と筋肉内のクレアチンが満たされていく。時間はかかるが、身体に優しく継続しやすい。
どちらの方法も最終的には同様の効果が期待できるため、目的や体質に応じて選択することが重要です。
まとめ|減量中でも“中身”を優先する選択
クレアチンは、筋力や筋肥大の向上をサポートするだけでなく、減量中の筋肉維持にも極めて有効なサプリメントです。
体重増加を恐れてクレアチンを抜くのではなく、脂肪を減らしながら筋肉とパフォーマンスを維持するという本来の目的に立ち返ることが、減量成功への近道となります。
今回の摂取再開をきっかけに、数字に囚われず、体の「中身」にフォーカスする重要性を改めて実感しています。クレアチンは、タイミングと目的に合わせて、的確に使いこなすべき“戦略的ツール”だと言えるでしょう。
